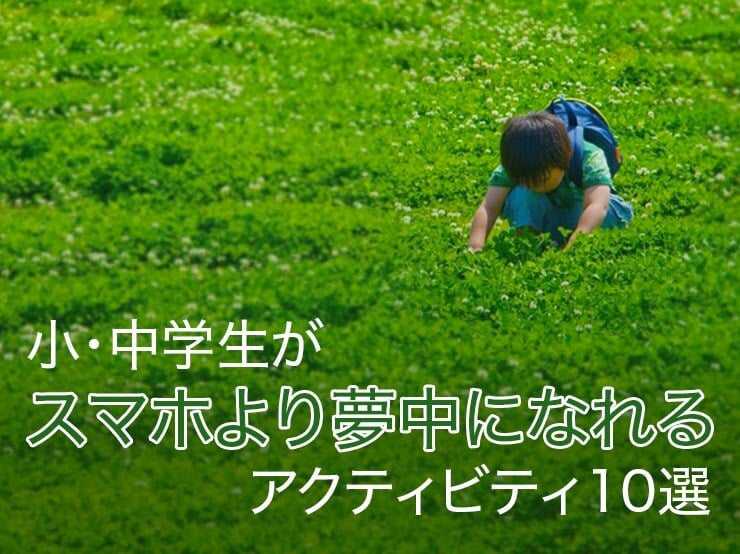
スマホやゲーム機がお家にあるのが当たり前になっている時代。
そして両親が共働きなのが当たり前になっている時代。
時代が変わると共に子どもたちの遊び方も大きく変わっています。
バンダイが 2018年3月に行った「小中学生の “遊び” に関する意識調査」によると、小・中学生に「普段、何をして遊んでいるか」聞いたところ、全体の第一位の回答が「スマートフォン・携帯電話・タブレット端末・パソコン」(45.3%)、第2位が「ゲーム(家庭用)」(40.1%)、第3位が「お買い物」(39.7%) という結果が出ました。
やはりデジタル世代に生まれた子どもたちの遊び方はデジタル機器にまつわるものが多いんですね!
分かっていても、数字で見ると少し衝撃的です。
皆さんもお子さんからスマホやゲームを取り上げると、「何をしたら良いか分からなくてつまらなさそうにしていて心配」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
子どもの身体・精神・脳の発達のためにも子どもがスマホやゲーム機以外の遊びをすることは大変重要です。
近年の子どもたちの体力低下については文科省も懸念していて、その理由の一つとして外遊びをする時間・場所・友だちの減少を挙げています。
でも、デジタル機器を使わずに身体を動かすメリットってそもそも何でしょう?
最も大きなメリットとして次の5つのことが挙げられます。
- 五感を刺激して脳を発達させる
- 太陽の光を浴びると夜に眠くなるホルモン「メラトニン」が分泌され生活リズムが整う
- 社会のルールを学べる。コミュニケーション力がつく
- 前頭葉が発達して集中力がアップする
- 思考力・想像力がつく
ご覧の通り、デジタル機器を使って目や手だけを使うのではなく、全身を使った遊びをすることは子どもの健全な発達に大きな役割を果たしているんですね!
親と子どもの世代の遊び方の違い
更に、親御さんの世代と比較して子どもたちの遊び場所にも変化が見られることも分かったんです。
皆さんは小・中学生の頃、放課後はどこでどのような遊びをしていましたか?
友だちと約束して公園に行って鬼ごっこをしたり、空き地を見つけて秘密基地を作ったり…
そんな思い出がある方も多いのではないでしょうか?
先ほど挙げたバンダイの調査によると、現在の小・中学生の主な遊び場所の第1位は自宅、そして第2位は公園。
デジタル機器での遊びをする子も増えましたが、外遊びの人気も衰えていないようでちょっぴり安心です!
少しびっくりするのが遊び場所の第4位にショッピングモールが入っているということや、他にも映画館や学童保育所がランクインしていることです。
現在の小・中学生の親御さんは自分たちが子どもの頃遊んでいた場所として自宅、公園、空き地を挙げているのに対し、時代の変化と共に子どもたちの遊び場所も変化しているようです。
しかし、子どもの遊び方がデジタル機器メインになってしまっているのは、子供たちが他の遊び方を知らないから、もしくは子供たちをとりまく環境のせいかもしれません。
実際に子供たちが遊ぶ環境について尋ねられたところ、「遊べる時間が少なすぎる」や「もっと屋外の遊び場を増やして欲しい」などの声が聞かれたそうで、子どもたちも現在のデジタル機器中心の遊び環境に満足していない様子がみられます。
親としても、子どもたちには思いっきり遊んでもらって、心も身体も健康に育ってほしいですよね。
でも、そうは言っても子どもたちにどんな遊び・アクティビティをさせたらいいのか分からない…
そんな方のために今回は子どもたちがスマホやゲーム機器のことを忘れて夢中になれる、お金のかからない遊びのアイディアを紹介します!
スマホより夢中になれるユニークな遊び・アクティビティ 10選
雨の日でもお家で楽しく出来る遊び
-
- 秘密の隠れ家作り
- ブランケットとクッションのお家・要塞を作る机や椅子、そして沢山のブランケットとクッションを使って特別に子どもたちに秘密の隠れ家を作らせてあげましょう。親子でやっても良し!子どもたちに任せるのも良し!今まで知らなかった子どもたちのクリエイティブな面が見られて親としてもとっても楽しいでしょう。ちゃんと後片付けを子どもたちが自分たちですると約束するなら、一晩だけその秘密の隠れ家で寝させてあげると子どもたちも普段と違うワクワク感が味わえます。
- 秘密の隠れ家作り
-
- まくら投げ合戦
- 「普段ならダメだけど、雨の日にとっておきの特別でまくら投げ合戦をさせてあげる」なんて言ったら子どもたちも大喜びでしょう。家族イベントにしてチームに分かれてやったら家族の絆もうんと深まるでしょう。予め壊れそうな物はしっかりとどこかに避けておいてくださいね。
- まくら投げ合戦
-
- 放課後、夜ご飯時のクエスチョンゲーム
- 最近、忙しかったり、家にいてもそれぞれ違うことをやっていたりでお子さんとの会話が少ないと感じることはありませんか?自分の子だけど、あまりどういう考えを持っているか知らない… ということはよくあります。そんな時のためにクエスチョンゲームを用意してみてください。やり方は至って簡単。少し大きめの単語帳やカードに普段から気になっている質問を一つずつ書いて箱にいれましょう。この際、お子さんにも子どもたちがいつも聞きたいと思っていた質問を書いてもらってください。日々の生活の中にふと抱いた疑問をどんどんと箱に貯めていくのも楽しいでしょう。出来上がったら、放課後や夕ご飯の際に1枚ずつランダムにカードを選び、お互いに質問してみてください。始めのうちちょっぴり恥ずかしいかもしれませんが、毎日時間を決めて日課にすることで、親子のみならず家族の絆が格段に深まるはずです。
- 放課後、夜ご飯時のクエスチョンゲーム
- インドア・ピクニックの日
- 雨の日だからってピクニックが出来ないなんてことは決してありません。子どもに素敵なピクニックを演出するチャンスをあげてみて下さい。大人では思いつかない突拍子のないことが起こるかもしれません。ピクニックをする前日か当日の朝に子どもにインドア・ピクニックをしていいことを伝え、どこで開催したいか、家の中のどこでしたいか、どういう風にデコレーションしたいかを考えて教えてもらってください。料理も勿論、子どもたちメインで用意してもらいます。外に遊びに行けなくても、子どもの創造力と自立心が目一杯刺激され、思い出に残る1日になること間違いなしです。
脳みそと体、どっちも鍛えられる外遊び・アクティビティ
-
- 公園さがしミッション
- 家の周りの地図を子どもたちに渡し、近所で出来るだけ沢山の公園を探すミッションに出しましょう!友だちや兄弟と一緒に先に計画を立てさせるのも冒険気分で楽しいかもしれませんね。このアクティビティは子どもたちが地図の読み方を学べるだけではなく、自分たちで遊び場を開拓することで外遊びへの興味を一気に上げられるいいきっかけ作りになります。
- 公園さがしミッション
-
- 優しさいっぱいの日 (Random Act of Kindness Day)
- 普段の忙しい生活の中だとついつい大人も子どもも自分のことで頭がいっぱいになってしまい、周りの人のことを考えるのをついつい忘れがちです。でも、人は決して一人では生きていけない生き物です。自分たちの生活がどういう風にどれだけの人に支えられているか子どもたちに考えてもらい恩返しの日を作りましょう。子どもたちに誰に何をしてあげたいかじっくり計画を立ててもらい、決行しましょう。時間をとって人に感謝の気持ちを表すことによって子どもたちの心も大きく育まれるでしょう。
- 優しさいっぱいの日 (Random Act of Kindness Day)
-
- 星観察ナイト
- 皆さん、最後にじっくり星を見たのっていつだったか覚えていますか?都会に住んでいると満天の星空を見るのはとても難しいですが、少し郊外に足を伸ばしてみるだけで星の観察スポットは意外に沢山見つけられます。一目星が広がっているのを見たら、スマホやデジタル機器のスクリーンの外にとっても広い世界があることを子どもに実感してもらうことが出来るかもしれません。
- 星観察ナイト
- 凧揚げ
- 何世代もの子どもたちを魅了してきた凧揚げ。子どもたちに自分の凧を作ってもらい、凧を飛ばしにいきましょう。このアクティビティは自分たちで凧の作り方を調べ、しっかりと飛ぶように試行錯誤して作り、実際に外に飛ばしに行くという3つの大きなプロセスから成り立っています。この間、子どもたちは新しい知識を自ら身につけ、成功は失敗からくるものなんだと学び、目標を成し遂げることの喜びを全て学ぶことができます。
その他
-
- バケットリストを作る
- 皆さん、バケットリスト(bucket list)という言葉はご存知ですか?これは死ぬまでに絶対やりたいことをリストにまとめたものです。よく大人だとスカイダイビングなどを挙げる人も多いですね。子どもたちに目標年齢を決めてもらい、それまでに成し遂げたいことのリストを作ってもらいましょう。一度リストを作ったら、そのリストを達成出来るように精一杯サポートしてあげましょう。目標を定めて、それを達成するために計画をたてるプロセス、そして目標を成し遂げたことからくる自信は、子どもたちにとって一生使えるスキルとなります。因みに、イギリスのチャリティ団体のナショナルトラストは “12歳までにするべき50のバケットリスト” なるものを作っており、その中には「木登りをする」、「日の出をみる」、「魚を捕まえる」などのものが挙げられています。英語ですが、もしよければ参考にしてみてください。
- バケットリストを作る
- 世界規模の宝探しに参加する
- 最後に紹介するのは、スマホの良さを使って生まれたゲームです。スマホで遊んでばかりいるともちろん子どもの健康に悪いかもしれませんが、スマホがあるおかげで外での遊び方も同時にぐっと広がっています。Geocache (ジオキャッシュ)というアクティビティを耳にしたことはありますか?これはスマホのGPS機能を使った世界規模の宝探しで、スマホを使ってヒントを得ながら隠されている秘密の宝を探し当てるものです。このアクティビティの良いところは、子どもがスマホの健康的かつ健全な使い方が学べること、探究心が育てられること、そして、近所にあったけど今まで知らなかった素晴らしい場所に出会える可能性があるということです。東京近辺にも4225個のジオキャッシュが隠されているようですよ!今週末、親子でさっそく探しに行ってみてはいかが?
スマホ以外の遊び方を子どもに学んでもらうには?
「んー、でもうちの子はやっぱりスマホやゲームに夢中で、別の遊びをするように促しても中々行きたがらなくて困ってる」、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そんな時には子どもがスマホやゲームの中で興味を示しているものを現実の世界の中でも楽しめることを見せてあげるのが良いでしょう。
例えば、犬や猫のゲームに夢中の子には出来るだけ動物に触れられるような場所に連れて行ってあげたり、戦いもののゲームが好きな子は子ども向けのサバイバルゲームに連れて行ってあげるなんていうのも1つのアイディアです。
まずは、日頃から子どもたちと出来る限り積極的にコミュニケーションをとり、その時の興味・関心を聞き出すところから始めてみてください。
今まで知らなかった子どもの意外な一面が見えると同時に、オフスクリーンの遊びやアクティビティに興味を繋げる第一歩となるはずです!
まとめ
さて、ここまで何故オフスクリーンの遊びが大切なのか、親子の世代間で遊び方がどのように変化したのか、そしてこれから出来る遊びやアクティビティのアイディアを紹介してきました。
時代が大きく変化し、様々なスクリーンが子どもの生活の一部になったからこそ、今までにも増してバリエーションに富んだ遊びが子どもたちの成長にとってとても重要になっています。
子どもたちは吸収が早いので、一度オフスクリーンの楽しみを見つけたら、どんどんと自分たちの興味や関心に沿ったアイディアが出てくること間違いなしです!
ここに挙げたアイディア以外にも良いアクティビティなどがありましたら、是非是非コメントで教えてください!
